 2024年9月よりアメリカミネソタ州にあるMayo clinicへ留学させて頂いております平成29年卒の西原敬仁です。現在約9ヶ月が経過し、留学記を書く機会を頂いたのでこれまでの体験と感じたことを1.研究2.英語3.プライベートに大きく分けて記させて頂きます。
2024年9月よりアメリカミネソタ州にあるMayo clinicへ留学させて頂いております平成29年卒の西原敬仁です。現在約9ヶ月が経過し、留学記を書く機会を頂いたのでこれまでの体験と感じたことを1.研究2.英語3.プライベートに大きく分けて記させて頂きます。
1.研究
Mayo clinicは1864年に設立された歴史のある米国内外から年間数百万人の患者を受け入れている臨床医療機関であり、基礎研究に関してもミネソタ・フロリダ・アリゾナに3つの主要なキャンパスを持ち世界有数の研究組織とされています。その本部であり今回私が留学している場所であるRochesterは「Med City」と呼ばれるほどMayo clinicの関係者と受診者で成り立っている街であり、その影響もあり非常に治安も良く穏やかな街です。
冬は非常に厳しく、年によっては豪雪になることもマイナス30度が続くこともある地域ですがその分それ以外の季節は過ごしやすく、これは私も来るまで知らなかったのですがタイミングがよければ近くからオーロラを見ることができます。私は渡米1ヶ月後に幸運なことに家から30分ほどの場所で見ることができました。
私が所属しておりますDr. Harmeet MalhiのラボはこれまでMASH;代謝機能障害関連脂肪肝炎の炎症の機序、特にマクロファージと小胞体ストレス・エクソソームの関連を主体に研究を進めてきました。それは現在も変わらず進行中ではありますが、自分の現在の主なプロジェクトは、過去の脂肪肝マウスモデル等から脂肪肝炎と高い関連があると考えられるもののまだ関連報告のないある蛋白質の脂肪肝炎との関わり、ひいては小胞体ストレスとの関連をin vitro/in vivo共に系統立てて証明する新しいプロジェクトに主に携わっています。また、近年がんや代謝疾患で注目されているcondensate(蛋白質やRNA分子が膜のない凝集体を形成し、遺伝子発現等をコントロールする機構)についても併せて研究を行なっております。
これまで臨床を主体としてきて、ほとんど基礎研究と関わっていなかった身としてはすべてを英語で一から学ぶことは多くの困難もありますが、これほどの研究施設で学べることは大変貴重な機会と感じております。
また、同じフロアの隣のラボではPSCの炎症と病態の解明、胆管癌や膵癌の新規薬剤の研究なども行われており規模の大きさと研究者の多さに刺激を受けております。
2.英語
想定はしていたことですが、留学が始まって一番困ったことはやはり言語の壁でした。義務教育・受験勉強の英語では生きた英語にとても太刀打ちができるはずもなく、留学前に少し準備をし、洋楽好きを自負している程度ではラボのミーティングの理解はおろか自分の思うことや考えていることを表現するのにも歯がゆい思いの連続でした。
今でもうまく聞き取れない・話せないことは多々ありますが、考え方を途中から変えて少しずつ進歩は感じているところです。ラボミーティングはボスの許可を得て、録音し振り返るようにしました。また、日常会話についても最初は時制や三単現のsなど細かいことを気にしながら話していましたが、それでは些細な会話もリズムよくできないと気づき文法は自然とできるようになるまでとりあえずは捨てることにしました。語彙については知っているか知らないかが全てなので可能な限り吸収できるようにして、その場で聞ける関係・タイミングであれば聞いて理解するようにしています。今では会話はリズムであり、英語が上手ではなくてもなんとかなるものかもと考えが変わってきています。
もちろん論文を読む、特に書く段階にあってはこの会話の理論は適応されず論文の英語力というのはまた違うものかと思います。
3.プライベート
体力はあまりないものの、精神力については人並みかそれ以上にはあると自負していた私ですが単身渡米生活はやはり堪えるものがあり、全く異なる文化と言語と食事・10月頃から急激に下がり始め気づけばマイナス30度になる冬・どんどん短くなる日照時間・さらに1月末にこちらのインフルエンザに罹患し39度近い高熱が出て1週間寝込んだ時は流石に日本が激しく恋しくなりました。その折に何気なく聞いた西野カナのラブソングになぜか涙しそうになった時に結構負荷がかかっているのだと気づいた次第です。
西野カナ事件を乗り越えてからは、アメリカの思考に多少染まったのか細かいことは気にしない・なんとかなる精神が少し定着し、先の英語の考え方の変化も相まってか同僚ではなく友人と言える関係も増えてきました。トルコ・ギリシャ・スペイン・インド・ドイツなど様々な国からFellowが来ており自分より若い人も多く、その国を代表する優秀な人間なのは間違いありませんが、お酒を飲むと結局同じ人間であり愉快な人達も多いです。これは単身の強みかとは思いますが、アウトドアアクティビティ・何気ない飲みの場・いかにもアメリカというパーティーにも呼んでくれるようになり、人間関係もさらに広げていければと思っております。また、彼らと関わる中で感じたことの一つに日本文化を好きで興味を持ってくれている人が本当に多いということです。ギリシャではビートたけしが非常に有名なようです。日本人が謙虚で礼儀正しい民族だというのも共通認識で持ってくれているようで、日本人である誇りと感謝と共にそれに恥じない日本人であろうとも感じています。
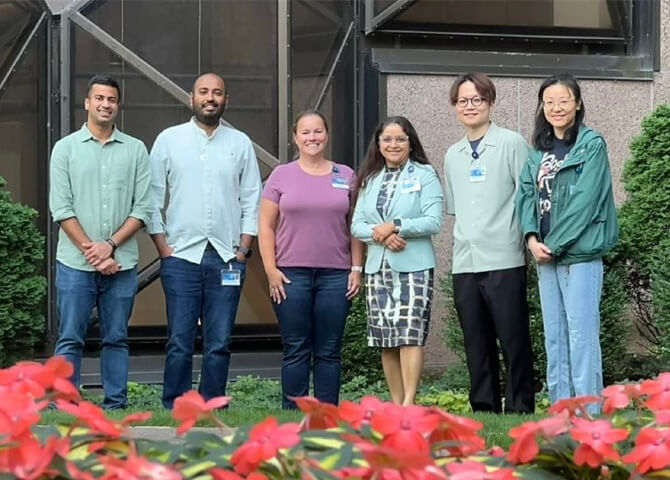

また、偶然ではありますが隣のウィスコンシン州(といっても車で3-4時間)に私より1ヶ月遅れて兄家族が耳鼻科のResearch Fellowとして留学してきており、クリスマスや姪っ子の誕生日など時間を共に過ごせているのも私にとってかけがえのない時間となっています。
現在アメリカの海外留学生に関しては新政権の影響で先行きが見えない不安定な状態となっており、兄もその影響もあって2年の予定が1年で帰国することとなり、私自身も不安を感じているところではありますが、現在自身のできる限りの努力と働きをしようと思う所存です。
以上まとまりのない留学記ではありますが、これらの貴重な経験をさせて頂いているのも宮明教授・赤澤教授をはじめ、チームの垣根を越えて送り出して頂いた胆膵グループの皆様、消化器内科の医局の皆様のお陰であり、心から感謝申し上げます。少しでも成長した姿をお見せできるよう、留学の経験を医局に還元できるように今後も精進して参ります。

